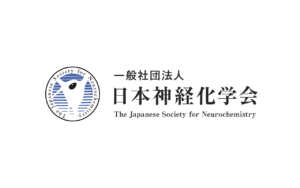私と神経化学 ―研究は、すべてが楽しくなければならない―

神経化学への入り口
私の出身校(上智大学理工学部)には50年ほど前の理工系学部としては珍しく「生物化学研究室」があり、慶応大学医学部出身の菊野正隆教授(故人)がおられました。「生物化学」「神経化学」という領域名も知りませんでしたが卒業研究の配属先に「生物化学研究室」を選び、卒業研究を進めるうちに「実験」が面白くなりました。そのまま大学院博士課程まで進み、漠然と研究者になりたいと思いましたが、具体的将来像などは全く見えません。修士課程を終わる頃に、菊野先生からイタリア・ミラノ大学薬理学薬剤学研究所(現・薬理科学分子生物学部)への留学を勧められました。ご自身が終戦後まもなく招聘留学された研究所で、所長のRodolfo Paoletti教授は、先生のミラノ時代の同僚でした。私は、イタリア政府給費留学生を目指してイタリア語の勉強を始め、1973年度の給費留学生に合格、タイミングよく1973年東京で開催された第4回国際神経化学会に来日されたPaoletti教授にお会いできました。当時、薬理学薬剤学研究所には、米国NIMH(National Institutes of Mental Health)のErminio Costa 博士の研究室から戻って間もない若く優秀な研究者がそろっており、新しい薬理学領域すなわち神経薬理学の研究拠点となりつつありました。私は、こうしてミラノで神経薬理学研究の世界に足を踏み入れ、それが「私と神経化学の出会い」でした。
ミラノではPaoletti教授から「君はCyclic AMP-man になるんだ」といわれ、DA-sensitive Adenylate cyclase の研究チームに加わりました。神経伝達物質DAとパーキンソン氏病の関連が明らかにされ始めた頃で、DA受容体としてのAdenylate cyclase の研究が盛んになっていたころです。最初の2年間は土曜日曜もなく夢中で実験をする日々でしたが、卒業論文作成に配属された5-6名のイタリア人学生が常に一緒でしたので、実ににぎやかで楽しい研究室でした。3年目、4年目は、研究室の学生たちをまとめる立場になり、私のイタリア語は飛躍的に上達しました。
次の転機は、1977年、NIMH のErminio Costa 博士の研究室でポスドクに採用され、「チロシン水酸化酵素のシナプス越え誘導」の研究を始めたことです。このシナプス越え誘導がcAMP 依存性であるかどうかで、Costa 博士とバーゼルのHans Thoenen 博士の間で論争が続いていました。ミラノ大学に行って間もない1974年のはじめ、Paoletti教授が私を一週間缶詰のトレーニングプログラムに派遣してくれました。ストラスブール近郊のモン・サントディール山頂に残る修道院で開かれたそのプログラムが、Costa博士を知った最初でした。Costa博士は講演で、チロシン水酸化酵素 (TH) のシナプス越え誘導の分子機構について解説され、同じくThoenen教授もその機構に関して講演されましたが、両博士の間では、サイクリックAMPが引き金となるかどうかで論争が続いていたのです。私は、情熱をむき出しにして議論するCosta博士の姿に魅了されました。
その後、ミラノで様々な機会にCosta博士の講演を聞き、博士の論理、仮説に基づいた研究の組立てを学ぶにつれ、いつか博士の下で研究をしたいと切望するようになりました。ミラノでの研究生活が四年目に入った頃、Paoletti教授が「米国で博士研究員になりたいなら紹介しよう」と二人の研究者の名前を挙げられ、その一人がCosta博士でした。私は迷わず、Costa研究室を希望しました。
Costa 研究室で与えられたテーマは、初代培養細胞を使ってTHのシナプス越え誘導がcAMP 依存性である事を証明することでした。テキサス大学のJack C. Waimire がウシの副腎髄質からクロマフィン細胞を単離培養する方法を発表したばかりでした。私のスーパーバイザー、A. Guidotti がテキサスまで行って彼に方法を教わり、それを私が習って培養を開始しました。設備などもまだ不備で最初の数ヶ月はコンタミネーションとの戦いでしたが、今になれば懐かしいことです。この初代培養細胞における「THのシナプス越え誘導」のcAMP 依存性の証明が、Costa研究室での最初の論文となりました1)。この現象は、シナプスの可塑性に繋がるといっても良いと思います。cAMP 依存性機構の研究はCREBの発見に発展していきましたし、他方でcAMP 非依存性機構の研究は、Thoenen 研究室の脳由来神経栄養因子の研究の背景になったと思います。
課せられたテーマにひとまず結果を出し、論文が受理されてほっとしたころ、クロマフィン細胞にオピエート受容体の局在が報告されました。内臓神経終末から放出され、その受容体に作用するオピエートは、クロマフィン細胞からのカテコールアミン(CA)放出を調節するのではと考えて実験したところ、ニコチン性刺激によるCA放出を選択的に抑制したのです。オピエート受容体を介した抑制であると確認したデータをCosta 博士に話し、実験を進める許可を求めたところ、初めは許可されませんでした。それでも実験を繰り返し、さらに確かめたデータを持っていくと、ついに論文にする許可をもらい、半年ほどの時間でできた論文が「Nature」に受理されました2)。機能的側面から「Co-transmitter」の概念を早期に論じた論文であったと自負しています。それまでの6年間は、文字通り「夢中」で実験にのめり込んでいた忘れられない時間です。
日本に戻って
日本に帰国してからのテーマである「開口分泌」または「神経伝達物質の放出機構」は、地味ではありますが生涯の研究テーマとなりました。これを選んだ理由は、日本に帰国してみると日本中が「リセプター」研究に集中していて、シナプス前機能を研究する人は極めて少なかった事が一つでした。競争相手の少ないテーマで、オリジナリティーの高い研究をと考えてのことです。上智大学には施設が無く、アイソトープ実験ができないことも大きな理由で、アイソトープを使わずに競争できるテーマはなんだろうかと考えているときに、カテコールアミンの電気化学的測定法(アンペロメトリー法)が実用化されました。Costa研究室で稼動していると聞いて、一ヶ月ほど戻ってその操作性と有効性を確かめた結果、これを武器にして行こうと決めました。アンペロメトリーの原理を勉強してみると、高速液体クロマトグラフィー等で分離しなくても直接CAを測定できると気がつき、細胞からのCA放出をリアルタイムで測定する方法を開発しました3)。この手法を発表した論文は、Journal of Neurochemistryに1週間で受理されました。1週間で、かつほとんど修正なしで論文が受理されたのは、後にも先にも、これが唯一です。この原理が、微小炭素繊維電極による単一細胞からの分泌測定に発展しています。開口分泌をいわゆるシングル・イヴェントとして測定解析するほかに、分泌顆粒の細胞内運動を可視的に測定し、分泌部位への顆粒供給機構の解析を進め、これに伴って、イタリアのAlessandro Riva 教授(現・カリアリ大学名誉教授)の協力で、細胞内部の走査電顕像を撮影してもらったのですが、このように様々な切り口で開口分泌を見ていると、わずか数十ミクロンの大きさしかないクロマフィン細胞の内部に、まるで宇宙のような広がりと魅力を感じて、どっぷりと研究に浸かりきっていました。研究者の幸せを感じていたと言ったら言い過ぎでしょうが、現役を退くまで研究が楽しくて仕方がありませんでした。この研究活動を通じて、国内外でいくつかの共同研究を進められたこと、研究室から武井延之君(新潟大学脳研究所、准教授)、今泉美佳君(杏林大学医学部、教授)、御園生裕明君(同志社大学脳科学研究科, 教授)等の優秀な研究者が育ってくれたことは大きな喜びです。
ちなみに、オピエート受容体の発見者、Solomon H. Snyder博士が自伝的エッセイの最後に、「重要なこと」と、次のように語っています4)。
結局、このエッセイで私が伝えたいと思ったことは、もし、さまざまな興味をもつことができれば、人生は最高であろうということである。芸術に携われば、科学的発見における生産性を上げることになるだろう。親として子どもを育てるには、メンターとして学生を、学部のスタッフを、あるいは同じ領域の専門家を育てると同じ取組みが求められる。ビジネスの世界で取引をすることは、現代科学のジャングルをさまようための鋭い洞察力を高める。いずれにしても、これらの活動はすべてが楽しくなければならない。そうでなければ、何のための苦労だろうか?
日本神経化学会と私
1979年の秋、菊野先生から上智大学に誘われ、足掛け6年ぶりに帰国しました。本学会には、帰国してすぐに入会しました。その頃は、ポスドク研究員に度々帰国できる経済的余裕など無く、6年間日本を離れていれば国内にも神経化学会にも知己はいません。幸いにも、その6年間に知り合い親しくなった黒田洋一郎先生(当時、東京都神経科学総合研究所、研究員)に、学会など機会あるごとに多くの方々に紹介して頂きました。入会して翌年、奥道後で第23回大会に参加したのですが、この大会がホテル貸し切りで行われたことも幸いして、帰国早々に本学会はじめ国内の神経化学領域に溶け込むことができたました。その上、上智大学で実験の立ち上げに苦労していると、東京都神経研での共同実験に誘っていただき、帰国後のブランクなく実験を継続することができました。黒田先生には、今でも感謝しています。
さらに共同研究の延長線上で、年1-2回のペースで小さな私的研究会も始まりました。この研究会では合宿形式で、午後はテニスに興じる時間もある一方、夜は大学院生も含めた時間無制限の議論で鍛えられました。その頃の本学会の大会では、発表10-15分・質疑応答10分のスケジュールがとられており、そのための良い訓練でもありました。神経化学会と、この小さなグループを通じては、多くの友人を得ました。その一人が(故)畠中 寛・元大阪大学教授でした。私がCosta研究室のポスドクのころ、彼は三菱化学生命科学研究所からHans Thoenen教授の研究室でポスドクとして同じ研究に取り組んでいたのです。それを知ったのは帰国してからのことですが、神経化学会や上述のグループを通じて、畠中さんという兄貴のような友人を得たのです。彼が十数年前に突然他界したことは、いまだに本当に悲しい事ですが、神経化学会の思い出から切っても切り離せない思い出です。
私が研究者として神経化学会に鍛えられたと感謝している点が、二つあります。一つは、若い研究者が積極的に一般演題の座長をさせられたことです。発表10分はともかく、10分の質疑応答時間にフロアーから質問が途切れたら、座長が10分間の質疑応答を持たせなければならないので大変です。私は座長を任された各演題について、質疑応答の10分間の座を持たせるための質問を用意して行きました。当時、一般演題の抄録は4ページあり、抄録審査によって選択されていたので、あらかじめ幾つか質問を用意することができたのです。これは、本当に勉強になりました。次に鍛えられた点は、言うまでもなく10分間の質疑応答です。神経化学会の質疑応答の厳しさは周知のところで、発表者にとっては自分の研究をブラッシュアップする上で貴重であると同時に、質問者・聴衆、とりわけ若い研究者にとっては大変勉強になります。研究を進めるうえでの論理の組み立て方や、データに基づいた考察の進め方を学ぶ貴重な機会でした。その後、会員数の増加と共に一般演題の応募数が増えた結果、質疑応答時間が短縮されてしまったことを残念に思っていましたが、質疑応答を10分に戻したセッションが復活しているようですから、ぜひとも継続して頂きたいと思います。北米Neuroscienceのように会員数が膨大な学会には、それなりの長所があるでしょう。しかし、本学会のように比較的小さな学会には、濃密な議論や時代に即した挑戦的な企画ができる、等の長所も大きいと思います。歴代理事長・大会長のご尽力で、本学会では最近そういった新しい試みが次々と企画されていることは素晴らしいことです。
「活発な質疑応答」は本学会の原点です。「日本の近代医学の父」と呼ばれるエルウィン・ベルツ博士は、明治35年4月2日に開かれた第一回日本医学大会の開会式に於いて次のように述べています5)。
抜粋: (前略)・・・しかしながら、この種の会議で最も重要なことは、わたしの考えますところ、講演ではないのでありまして、よしんばそれが非常に優れた先生から出たものであるとしても、そのような講演ではなく、種々様々な意見の活発な交換、ことに各個人の経験―もちろんこれは常に多少異なる結果となるものなのですが―その経験の活発な交換であります。(中略)・・・専門家にとってこそ、日ごろあまりにもかたよった仕事をしているのですから、こんな機会に全般的研究と自己の専門領域との関係を知ることは特に価値があるわけです。(後略)。
今からおよそ100年前のベルツ博士の言葉ですが共感を覚えます。本学会の発展を祈る気持ちを、その共感に託して皆様に伝えたいと思います。
さて、1993年、文部省(現・文部科学省)科学研究費に「神経化学・神経薬理学」の細目が設けられました。これは、数年にわたる佐武 明先生(現・新潟大学名誉教授、本学会名誉会員)のご尽力のお陰ですが、その数年間、笠井久隆先生、高坂新一先生、小宮義璋先生(故人)と共に、佐武先生のお手伝いができました。私が神経化学会に貢献したことがあるとすれば、このお手伝いです。細目が設けられたことで神経化学会は、会員の研究に一段と幅が増して発展したと思います。私は、御子柴克彦理事長のもとで副理事長を務めさせて頂きましたが、副理事長として特にこれという貢献もできませんでした。しかし、一会員として、大会の度に植村慶一先生(故人)を中心として開かれるテニス大会を通じて、大学院生をはじめ多くの会員の方々の親睦促進にお手伝いができたことは、楽しい思い出です。
この拙文を寄稿するにあたっては、出版・広報委員長 等 誠司先生から、「研究や学会活動を存分に楽しんできた姿を、若手に見せることが大切だと思います。」とのお考えを添えてご依頼を頂きました。研究から離れてすでに10年余が過ぎた身でも、そのような形で学会のお役に立てるならと思い、寄稿させて頂きました。紙面の都合で、研究生活のさまざまな局面でお世話になった先生方、親しくさせて頂いた方々のお一人お一人に感謝の言葉を述べることができませんでした。この場を借りて、心からの感謝を申し上げます。
References
1) Kumakura K, Guidotti A, Costa E. Primary culture of chromaffin cells: Molecular mechanisms for induction of tyrosine hydroxylase by 8-Br-cyclic AMP. Mol. Pharmacol. 16: 865-876, 1979.
2) Kumakura K, Karoum F, Guidotti A, Costa E. Modulation of nicotinic receptors by opiate receptor agonists in cultured adrenl chromaffin cells. Nature 283: 489-492, 1980.
3) Kumakura K, Ohara M, Sato GP. Real-time monitoring of the secretory function of cultured adrenal chromaffin cells. J. Neurochem. 46: 1851-1858, 1986.
4) 『メンター・チェーン』ロバート・カニーゲル著、熊倉鴻之助訳 (工作舎、2020年)より
5) 『ベルツの日記』 トク・ベルツ/編 菅沼竜太郎/訳 (岩波書店、1979年)より
(2021年10月原稿受領)